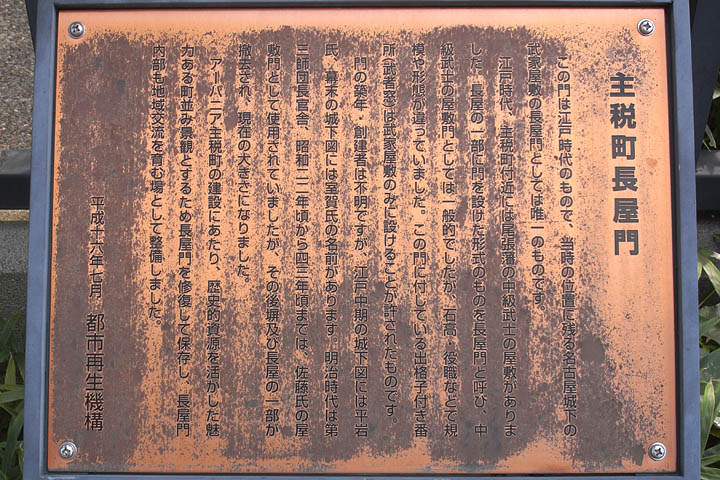『鸚鵡籠中記』の忠臣蔵―主税町
元禄十六年(一七〇三)二月四日、無事、吉良上野介の首をはね、主君の仇を報じた大石内蔵助は、細川越中守の屋敷で切腹をした。行年四十五才である。
『鸚鵡籠中記(おうむろうちゅうき)』の作者、朝日文左衛門は、この年、三十才、御畳奉行であった。 文左衛門は、大石内蔵助が切腹をする半月ほど前の一月十七日の日記に「正月十七日、連、安く堕胎」と記している。
妾の連が妊娠をした。とてものことでもないが、恐い妻のけいに話せるものではない。中絶をしたが、思ったほども費用がかからなかった。ほっとして「安く堕胎」と記したのであろう。
あら楽し思ひは晴るる身は捨つる浮世の月にかげる雲なし
と武士としての本懐をとげた満足感を辞世の歌にしたため腹を切った内蔵助と中絶費が思ったよりもかからなかったことに安堵している文左衛門との、同時代に生きた二人の対比がいかにも面白い。
『鸚鵡籠中記』には、浅野内匠頭の刃傷事件から討ち入りまでの記事が散見している。当時、名古屋に、この事件がどのように伝聞していたかを知る恰好の材料であろう。
浅野内匠頭が殿中で刃傷事件を起こした元禄十四年三月十四日の記述は次の通りである。
於江戸喧嘩有。毎年春勅使・院使江戸へ有之。高家衆吉良上野助と、其外大名両人宛御馳走に懸る事也、今度も上野助と浅野内匠と外に何の某と云者懸る。某は賂を吉良へ遣して、首尾を頼む。内匠にも音信可遣由、家老すすむといへども、賂を以て諛事なしとて、少も不遣。吉良は欲深き者故、前々皆音信に而頼むに、今度内匠が仕方不快とて、何事に付而も言合せ知らせなく、事々に於て内匠齟齬する事多し。内匠之を含む。今日於殿中、御老中前に而吉良云様、今度内匠万事不自由ふもとをり不可言、公家衆も不快と被思て云。内匠弥含之座を立。其次の廊下に而、内匠刀を抜て詞を懸て、吉良か烏帽子をかけて頭を切る。吉良駭て急ぎくぐりの様成所をくぐるを、後から腰を切といへども、共に薄手に而つつがなし……。
記事は、まだ続くが長いので省略する。
十四日の日記に載せてあるが、殿中のできごとが、その日のうちに名古屋に伝わるはずもないから、この部分は、後日に書き入れた部分である。内匠頭の上野介への刃傷事件を、文左衛門は「喧嘩」であると断定している。紹介した記事の後に、さらに「今は勅答も末終、殊に殿中の喧嘩は是非を不論。先太刀打者非分になる事也」とくりかえし論じている。
喧嘩両成敗という当時のしきたりに即していえば、内匠頭だけが、その日のうちに切腹を命ぜられ、上野介には何のおとがめもないというのは理不尽な裁きである。四十七士の討ち入りは、片手落ちの裁きによってもたらされたものだ。上野介の言い分によれば、刃傷は内匠頭の乱心のために起こった事件である。とすれば、内匠頭は一方的な加害者、上野介は一方的な被害者になる。内匠頭は罰せられ、上野介には何のおとがめもなかった。
乱心による刃傷という綱吉の裁きを、文左衛門は喧嘩であるとしているところが面白い。
刃傷の原因も、さまざまな説がある。
内匠頭の精神分裂症が原因である。あるいは、赤穂と吉良との塩の製法や販売競争の激化が原因である。うがった説では船橋聖一の、上野介の内匠頭の妻、阿久利への懸想説がある。
文左衛門は、原因を「賄」であるとしている。賄賂を贈らなかったので齟齬をきたしたというのである。「吉良は欲深き者」とする文左衛門の評言はきびしい。
内匠頭が上野介に切りつけたのは、眉間が先か背中が先かの二説あるが、文左衛門は「頭を切る」と眉間説である。
『鸚鵡籠中記』に、赤穂事件が、次いで登場するのは、元禄十四年(一七〇一)四月七日の赤穂城の明け渡しの日である。
頃日、赤穂之家中一党し、領内へ、他領者を一人も不入。城請取には、脇坂淡路守・木下肥後守趣く。赤穂の家中所存を欲すといへ共、内匠一家之左門等能示し、内匠喧嘩之埒ならば、尤相手をも無事に置まじけれ共、只殿中狼藉之趣に而、切腹なれば、誰に対し恨を述ん、又内匠一家之者、かく言からは、是に違背せば、甚理なしなど、言聞せ、今月十九日に、両人無事に首尾能城請取。
おもおもしい雰囲気の中で、城が明け渡されたことがよくわかる記述である。 元禄十四年十二月十三日の日記に、次のような記述がある。
去比から、勢州亀山に百三十人余、松原に屯し、幕を張、鉄炮等を持者もあり、食事は餅等を買て給。宿を不求と、赤穂の浪人なりと云。
赤穂浪人が討ち入るという期待であろうか。鉄砲を持ち、百三十人もの浪人が徒党をくみ、東上をするという噂が伝わってきた。 亀山にたむろする浪人のうわさから一年後の元禄十五年(一七〇二)十二月十四日に討ち入りが行われた。
夜、江戸に而、浅野内匠家来四十七人亡主の怨を報ずると称し、吉良上野介首を取り芝泉岳寺へ立退。
なんとも素っけない記事である。あまりの素っけなさに、『元禄御畳奉行の日記』で、神坂次郎は「赤穂浪士の討ち入りの華やかさはのちに歌舞伎作者や講釈師たちの手によって飾りたてられ(竹田出雲の名作『仮名手本忠臣蔵』は、浪士切腹から四五年後の作)、歳月とともに醗酵し、潤色され、それが事実だと観客たちに信じられるようになってから、爆発的な忠臣蔵ブームが湧きおこったのであろう。が、これはあくまでも『忠臣蔵』ブームであって、赤穂浪士ブームではない。すくなくとも、討ち入り直後、名古屋城下で士庶が『元禄の快挙』に拍手をおくったという事実はない」と記している。
はたして、そうであろうか。亀山での赤穂浪士のうわさなどを考えれば、討ち入りの待望論があったはずである。 討ち入りをどのように判断してよいかは、文左衛門ばかりでなく、老中たちも悩みに悩んだ。だから四十七人の義士に対する処分にも日数がかかったのである。 妻を恐れ、酒におぼれていた文左衛門のような武士でも、赤穂事件には多大な関心を持っていたのである。